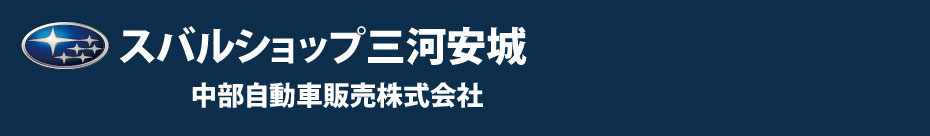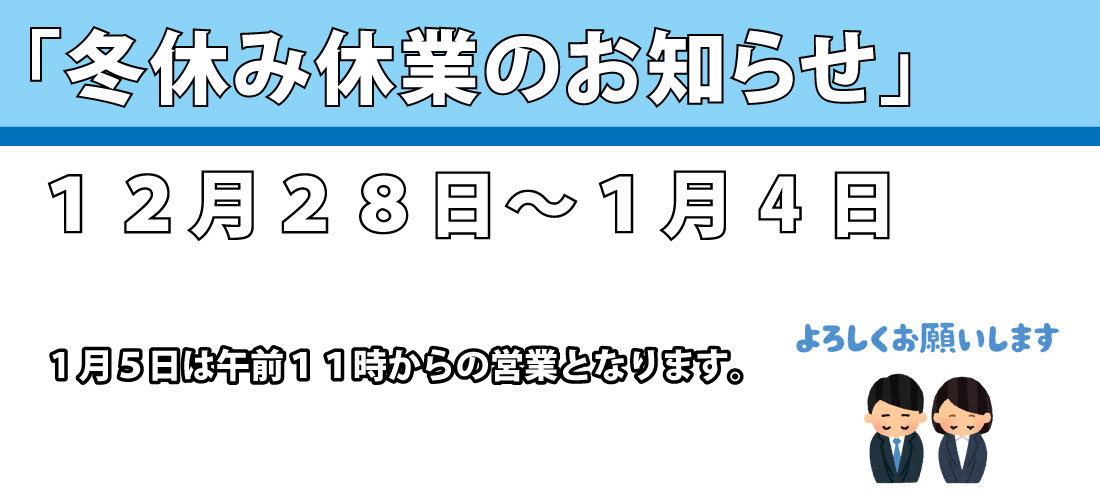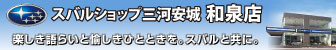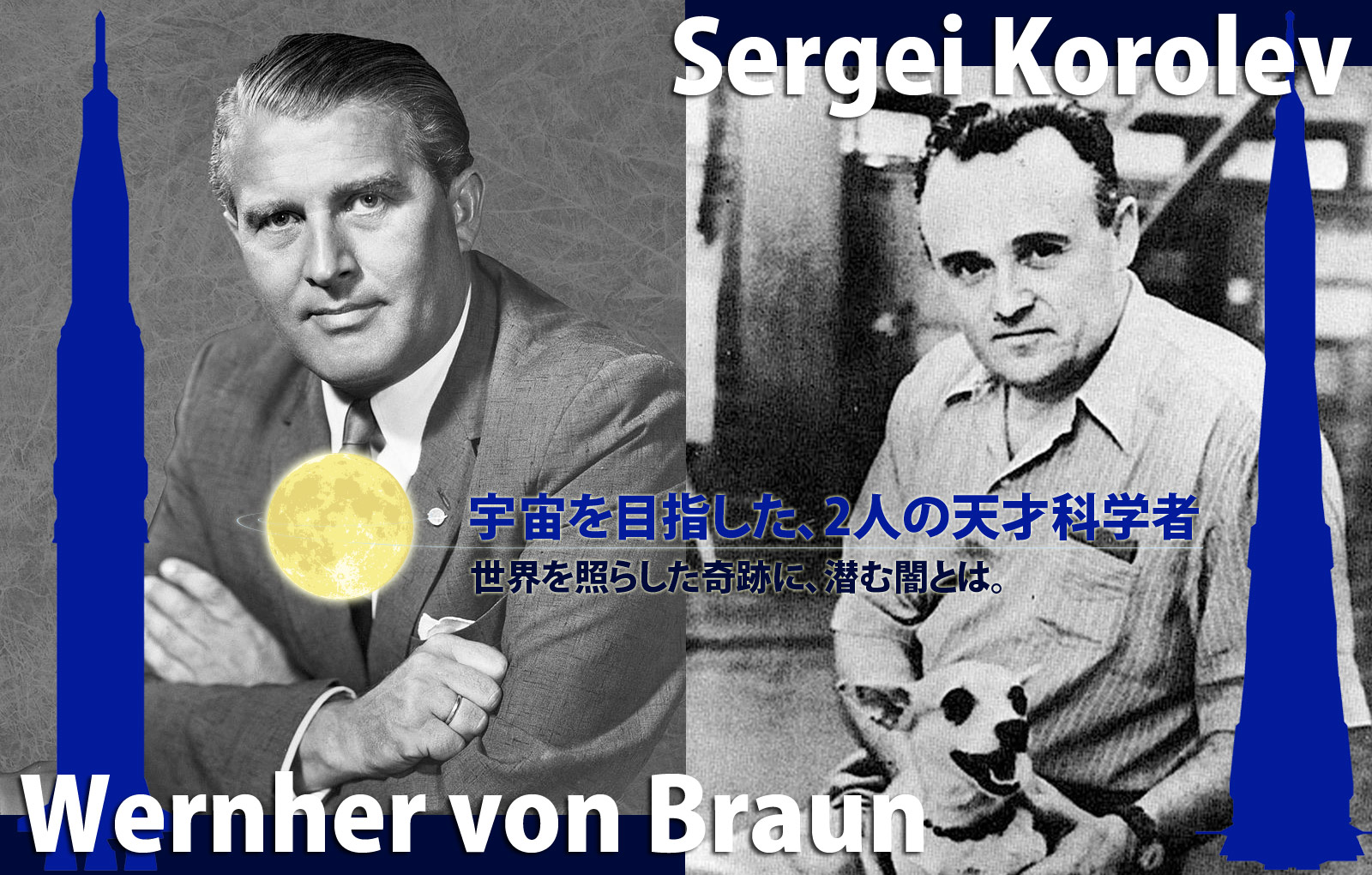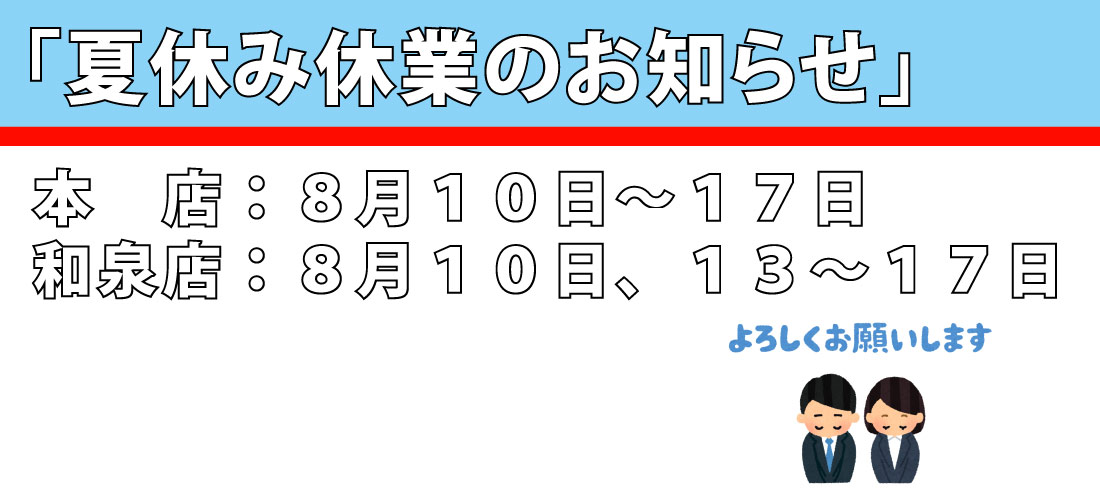オートサロンとCES、進む二極化。 [2024年02月04日更新]

ニュース ピックアップ [ モーターショー 最新情報 ]
衝撃のニュース満載!!東京オートサロン2026開...
2026年01月10日 スバル
中部自動車販売の冬休みのごあんない。...
2025年12月27日 スバル
スバルが、東京オートサロン2026出展概要を発表...
2025年12月26日 スバル
スバルBEV戦略に大異変!「2025方針」を徹底...
2025年12月12日 スバル
Japan Mobility Show 2025...
2025年10月29日 スバル
Japan Mobility Show 2025...
2025年10月30日 スバル
思案に熟慮を重ねに重ね、Youtubeチャンネル...
2025年10月25日 スバル
スバル内部に大変化??「Japan Mobili...
2025年10月20日 スバル
次のページ>>1 2
盛り上がったオートサロン、海の向こうではCESが盛況。
2024年1月12日〜14日にかけて、今年もカスタムカーの祭典である「TOKYO AUTO SALON 2024」が開催されました。STIやGR、NISMOのようなワークスチューナーを中心に、大小様々なチューナーが勢揃い。OEMもこれに加わり、ホットモデルの発表やモータースポーツの体制発表を実施。その会場をモリゾウ氏が日々忙しく飛び回り、盛り上がりに華を添えました。
オートサロンの最大の特徴は、親しみやすさと距離感でしょう。日本各地から集結したチューナーと直接カスタマイズの相談ができますし、そこかしこで有名レーシングドライバーのトークショーが行われ、華やかなレーシングカーが所狭しと並べられています。ファンにはたまらないイベントなのは間違いありません。
同じ週、太平洋を挟んだ米国ネバダ州ラスベガスでは、業界向けの電子機器の見本市「CES」が開催されています。その盛り上がりは凄まじいものがあり、すべての技術トレンドはここから始まる、と言っても過言ではないほど。自動車産業も例外ではなく、所謂IoT系の技術はこのCESを発表の舞台としています。今年はソニーホンダモビリティが新型BEV「アフィーラ」を発表するなど、自動車産業側の興味は年々高まっているようです。スタートアップ企業が多いのも特徴で、独立系エンジニアリング企業や技術コンサルタントなどが、OEMとの接点を見付ける稀有な機会ともなっているようです。
オートサロンとCES。愛すべきクルマと無機質なモビリティ。
この2つのイベント。その内容は、全く対極的。オートサロンが参加型なら、CESはそもそも一般開放でさえありません。並ぶクルマを見ても、技術的に見ても、そこに集う人々を見ても、その内容は全く正反対だと言えます。
オートサロンの根幹は、伝統的自動車趣味。サウンドをこよなく愛し、ドライブに興奮と悦楽を求める。その会場では、クルマは単なる移動体ではなく、愛おしい人生のパートナー。日本のカスタムカーは世界的な注目度も高く、自動車がより魅力的であるために、必要不可欠なイベントへと成長を遂げています。自動車好きなら、絶対に笑顔になる。そんな素晴らしいイベントは、オートサロン以外にありません。
一方のCESは、BtoBの技術展覧会。それ故、OEMの立場を反映して、内容はCASEが中心。趣味的・情緒的内容とは程遠く、クルマというよりモビリティ、愛車というより社会インフラ。CESの最大の強みは、国境を越えた異業種交流でしょう。電子機器という括りしかないため、ハード・ソフト問わず様々な業種のエンジニアが集うのです。そこで起こる化学変化と、全く新たな協業。未来を切り拓くカギが、そこかしこに転がっているのはCESだけでしょう。
心踊らせ魂揺さぶる自動車と、無機質にインフラ化していく自動車。ドライバーレスとドライバーファースト。個人所有と社会インフラ。衝動・興奮と無味・無臭。2つのイベントは、全く相反する2つのベクトルが指し示す、自動車の未来をそのまま体現していると言えます。
自動車産業が熱くフォーカスする、2つのベクトル。
自動車産業には今、全く相容れぬ2つのベクトルが併存しています。
一つのベクトルは、プレミアムブランドのドーピングモデルに象徴される、趣味性の追求です。分かりやすく言えば、デカイ・速い・高い=偉い。多分に前時代的ですが、これも自動車文化の大事な一面です。自動車文化は元来、貴族階級の好奇心に端を発するもの故、性能・豪奢さの優位性は存外に重要なのです。もちろん、過剰な装備・性能は、交通手段としてはムダでしょう。地球環境保全にとっては、害悪ですらあります。しかし、人類は太古よりムダを尊んできました。ムダは豊かさの象徴であり、ムダこそが文化なのです。自動車産業が100年来、ずっと高い利益率を維持してこれたのは、自動車が自己表現・自己顕示の手段であり、趣味の対象であったからです。
もう一つのベクトルは、モビリティ化です。脱炭素+自動運転+シェアリング+ネットワークサービス、つまりCASEの具現化です。自動車の個人所有から脱却し、シェアリングへ移行。自動車の総量を最適化しつつ、完全電動の自動運転車両のみの通行とすることで、交通インフラ全体で脱炭素化を推進するのです。二酸化炭素排出は、減らせる所から減らすしかありません。ムダを省くしかないのです。ここ数年、自動運転やシェリング技術に停滞感が否めませんが、それは電動化が最優先されているから。電動化技術が一巡すれば、モビリティサービスの実現へ向けて動き出すはずです。私たちが自動車の所有者であるより利用者である方が、持続可能な社会の実現に向けて理に適っているのです。
OEMが最も恐れる、車体製造サプライヤーの未来。
自動車産業主要17社の研究開発費は約11.8兆円に到達。前年度比で13%増加し、過去最高を記録しています。OEMは新たな4つの技術領域「CASE」の研究開発に必死に取り組んでいます。新時代の趨勢を決定付ける最優先の経営課題ゆえ、形振り構わず巨額の投資を行うことで、必死に未来への道標を探そうとしているのです。
OEMが最も恐れるのは、自分たちが「車体製造サプライヤー」に落ちぶれること。e-Axle、バッテリ、自動運転・シェアリングを含めたネットワークサービスなど、主要技術領域が丸々外注になれば、自らの取り分が目に見えて減るだけでなく、市場の主導権さえ手放すことになりかねません。
このような背景で進んでいるのが、業界再編です。フィアット・クライスラーとPSAが合併してステランティスが誕生。国内でも、スバル、スズキ、いすゞがトヨタとの関係強化を図るなど、CASE時代を見据えた企業連合が形成されつつあります。また、ホンダとソニーなど、今後は業界の垣根を越えた企業連合に突き進む可能性も考えられます。
ただ、これは始まりに過ぎません。都市交通の一翼を担うモビリティサービスで覇権を握るのは、一体誰なのか。それが確定した時点で、さらなる業界再編がスタートすることでしょう。もしかすると、e-Axleや自動運転システムを供給するティア1がその規模を拡大し、OEMを傘下に収める下剋上もあり得ます。はたまた、今は姿も形もない新興企業が業界を席巻し、自動車産業全体を影響下に置くまでに成長するかも知れません。だからこそ、OEMは必死なのです。
どのメーカーでも同じ。モビリティサービスの未来。
ただ、CASEが実現する未来は、OEMにとって必ずしも歓迎すべきものではありません。
モビリティは、無人の完全自動運転。利用者はスマホからアクセスし、目的地までドアtoドアで移動します。乗り合い・乗り継ぎが必要な場合でも、スマホに移動プランが表示され、乗降を指示してくれるので、最短・最適ルートでの移動が可能になるでしょう。移動制約者に対しては、自治体補助による完全ドアtoドアのプライベート利用が提供されるはずです。
もし、このようなサービスが実現すれば、人々は自動車のオーナーでもなく、ドライバーでもなくなります。人々は、単なる利用者に過ぎません。バスや鉄道に乗る時、その車両が何処製なのか気にする利用者が居ないように、そのモビリティが何処製なのか誰も気にしなくなるでしょう。そもそも、交通インフラとはそういうものです。
モビリティサービスを実現するには、恐ろしく大規模かつ非常に緻密なソフトウェア開発が不可欠です。しかし、既存の自動車技術の延長線上にはない技術領域ゆえに、その実現の最短距離に居るのはどう考えてもOEMではありません。主導権を握るのはGAFAだと考えるのが自然でしょう。もし、GAFAに先を越されれば、OEMは車体製造サプライヤーに落ちぶれる他ありません。それでは、OEMは望まぬ未来を実現をするために、CASEに巨額の投資を行っていることになります。
だからと言って、OEMが時代の流れと社会的使命に抗うのは不可能でしょう。モビリティサービスは、都市から交通事故を撲滅し、移動の制約を完全に廃し、ムダな二酸化炭素排出をストップするために提供されるもの。持続可能な社会へ向けた、時代の要求なのですから。
デカくて速いBEVが明らかにする、OEMの絶体絶命の危機。
欧州プレミアムブランドが競って開発する、ハイパフォーマンスプレミアムBEV。航続距離を稼ぐ巨大なバッテリと、瞬間的に高出力を発揮するe-Axle。3t近い物理法則から逃れるための、巨大なタイヤと堅牢なボディ。デカくて、重くて、速くて、高い。結局、電費はサイアク。誰が考えても物理法則に反する、本末転倒な商品企画です。
しかし、その狙いをよくよく考えてみると、相反する2つのベクトルを強引に一つにした結果だと気が付きます。趣味性の高いクルマ創りとCASE技術の強引な合体。そして、モビリティ化への抵抗。CASEを総合技術ではなく、単体の要素技術として旧来の商品企画に適用した結果が、「デカイ・速い・高い=偉い。」のBEV版。高度な運転支援システムとネットワークサービスを満載したハイパフォーマンスBEVをサブスクリプションで提供する、という方程式なのです。
BEVの最適解がシェアリングのシティコミュータであることは、誰でも知っています。しかし、OEMはその流れを加速させることはできません。なぜなら、その流れはそのまま「どれに乗っても一緒」のモビリティ化へと繋がっていくからです。それを知ってるからこそ、BEVの流れを最適解から強引に捻じ曲げて、ハイパフォーマンスプレミアムBEVへと繋げているのです。
ハイパフォーマンスプレミアムBEVは、OEMが高収益体制という自らの牙城を守るために、絶対不可欠な存在です。ただ、そんなハッタリが長く続く訳がありません。所詮は、虚仮威しです。近い将来、化けの皮が剥がれて、消費者にソッポを向かれるのは間違いありません。
OEMの危機感から生まれた巨大企業連合と巨額投資。
近年、自動車の価格は恐ろしい速度で上昇し続けています。5年前に400万円の予算を要求したノア/ヴォクは、2年前には450万円に達し、今や500万円を伺う様子。価格改定・値引き減少が直接的要因ですが、その背景には装備の追加・資材調達費の上昇があります。ただ、だからと言って、たった5年で20%も値上がりするのはおかしな話です。もちろん、それらは表向きの理由。主因は調達費の上昇ではなく、CASE周りの巨額投資です。
トヨタとデンソーは、2022年11月にキオクシア、ソニー、ソフトバンク、NEC、NTT、三菱UFJ銀行とともに、半導体メーカー・ラピダスを設立。1年後の2023年12月には、日産、ホンダ、マツダ、スバルとともに、ルネサスエレクトロニクス、ミライズテクノロジーズ、パナソニックオートモーティブシステムズらと自動車先端SoC技術研究組合を設立。自動車向け半導体だけでも、オールジャパン体制を組まねばならないほど、深刻な課題となっているのです。
例えば、BEVの制御に不可欠なインバータ。そのコアとなるのが、パワー半導体です。最新のトレンドは、高出力密度を実現可能なSiC。従来のIGBTより数段高価なSiCは、電費を大幅改善可能なためBEVには必須なのですが、既にOEM間でシリコンウェハ争奪戦が始まっているのです。確保したシリコンウェハ量=生産可能なBEV台数ですから、OEMも必死。畑違いの分野ですから、OEMが親分風を吹かせて左団扇、などあり得るはずもなく、企業連合を組んでその確保に血眼になっているのです。
CASEの「E」だけでこの状況ですから、OEMが如何に厳しい状況に置かれ、巨額投資を迫られているかが理解できるでしょう。
次のページ>>1 2
スバルショップ三河安城 店舗案内

>>最新情報一覧